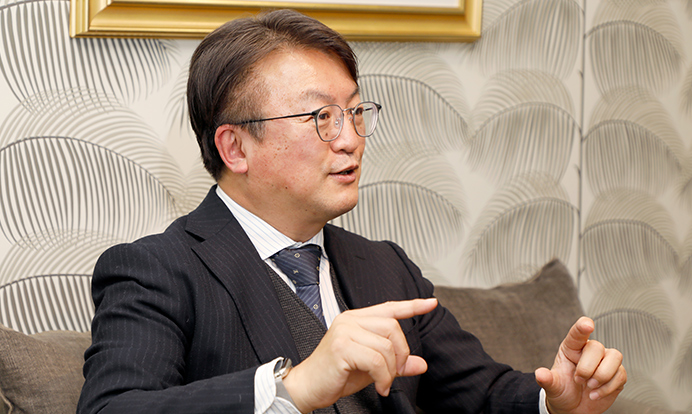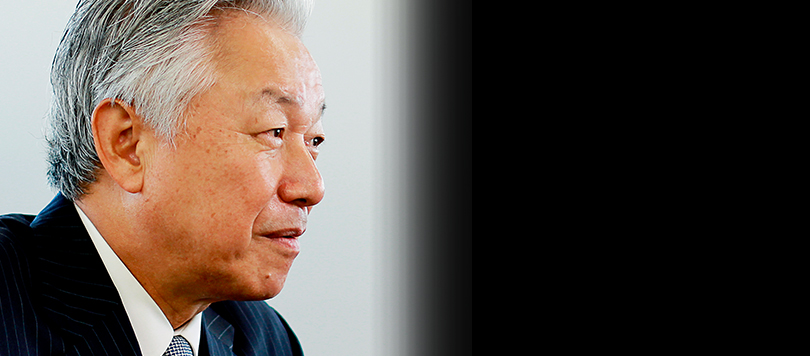時代のニーズに応じてさまざまな地図調製を手がける。
「創業時は戦後間もない頃だったので、一番の得意先は農林水産省でした。なぜなら、当時の日本にとっての大きな課題は食糧増産。どこがどういう土壌で、どんな作物が適しているかについての研究成果を反映した地図などを、調製する業務が多かったのです」と語る、代表取締役社長の五本木秀昭氏。
その後、高度経済成長期に入って国土開発が盛んになると、鉄道や道路のルート検討のための基礎資料としての地図の調製が増加し、環境問題への関心が高まると、自然保護のための植生分布図の調製業務が増えた。このように、内外地図は時代のニーズに応じて様々な地図調製を手がけてきた。
五本木氏が、大伯父が興した会社である同社に入社したのは1986年。その頃には各省庁の主題となる地図は概ね完成していて、増刷や比較的単純なアレンジが業務の中心になっていたという。
「私の入社時は、ルート営業で顔を出せば『地図屋さん』と呼んでもらえて、何の問題もなくお仕事がいただける時代でした。ニッチな業界で競争相手も少なく、安定した利益を出せていた。非常に楽でしたね。ただそれだけではつまらないので、自分なりの特色を出したくて、雑談の際に『こんなこともできますよ』と提案はするようにしていました」
当時は、製図も印刷もまだアナログの時代。手作業による地図調製は、版画制作に近い工程を要した。ベースの図に情報を重ね合わせ、フィルム伸縮の際に生じる誤差を計算しつつ、相対的な位置関係が崩れないように基準の中に納めるためには、熟練職人の技が不可欠。特殊技術ゆえ、新興企業が参入しにくい業界だったのだ。
しかしその状況は、デジタル技術が普及したことで一変した。コンピュータやグラフィックソフトがあれば、誰でも比較的容易に正確な地図の制作や複製が行えるようになった。地図調製は特殊技術としての優位性を失い、価格競争の結果、技術・体力のない会社は次々と淘汰されていった。内外地図が被った打撃も、少なからぬものがあったという。そうした中で同社は、デジタル化への対応に加えて、地図調製の枠を超えた業務を積極的に展開することで窮地を乗り切ってきた。
「特殊技術による差別化にこだわっていては先がない。従来は研究機関などが行った調査結果のデータを地図に落とし込むだけでしたが、地図調製の上流を目指し、調査業務も手がけるようになりました」